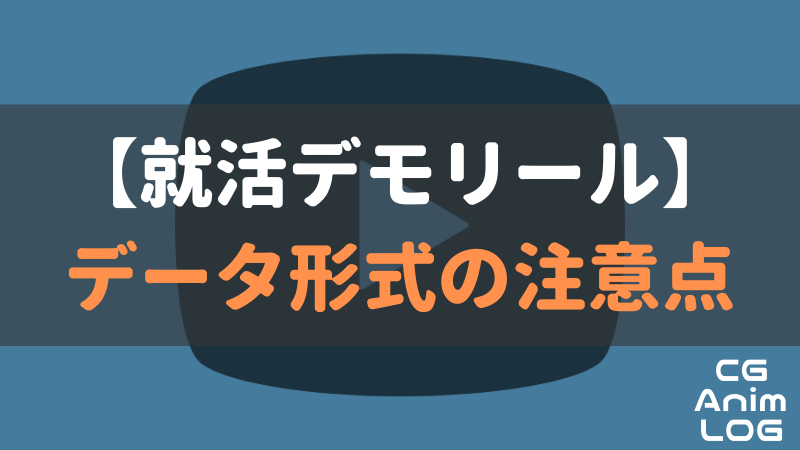デモリールを作るうえで気をつけた方が良い点についてまとめました。
就活デモリールの「動画データ的な作法」について書いています。
デモリールの基本的な形式について知りたい人向けの記事です!
デモリールの基本的な形式について知りたい人向けの記事です!
デモリールのポイント
- 動画の大きさはHD(1280×720)あれば十分
- 形式は「h.264圧縮のmp4」が軽い・きれい・汎用的
- フレームレートは統一する
動画サイズはHDで十分
アニメーションデモリールの解像度は、HDサイズといわれる「1280×720」あれば必要十分です。
これより小さいと何をしているか分かりにくかったり、揺れものなど細かい部分の動きが分かりづらくなります。
フルHD(1920×1080)ぐらいならありですが、それ以上大きくてもファイルサイズが大きくなるだけであまりメリットはありません。
動画形式はh.264/mp4がおすすめ
動画のファイル形式は「h.264コーデックで圧縮したmp4」が良いです。
他には「avi」や「mov」などありますが、コーデックによって画質が劣化したり、ファイルサイズが肥大化する、環境によっては再生できないこともあります。
h264/mp4形式の動画は画質の劣化が少なくファイルサイズは小さくなるため、提出用動画としては最適です。
エンタメ系CG会社ならh264/mp4形式で再生できないということはまずありません。
フレームレートは統一する
デモリールの収録作品とデモリール自体のフレームレートは統一するようにしましょう。
たとえば30FPSで作った作品を24FPSで書き出すと、途中のコマが消えて絵が飛んだようなアニメーションになります。
(1秒間あたり6コマ消える)
逆に24FPSで作った作品を30FPSで書き出すと、同じ絵が2コマ続いて一瞬カクついたようなアニメーションになります。
(1秒間あたり6コマ余計に表示される)
収録作品を通してフレームレートは統一して、書き出すデモリールも同じフレームレートにする必要があります。
デモリール制作ポイントまとめ
- 動画の大きさはHD(1280×720)あれば十分
- 形式は「h.264圧縮のmp4」が軽い・きれい・汎用的
- フレームレートは統一する